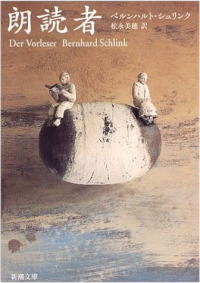
ベルンハルト シュリンク(著)
文庫: 258ページ
出版社: 新潮社 (2003/05) |
Amazon.co.jp
スイスで出版された原書を、キャロル・ブラウン・ジェンウェイが格調高い英語に翻訳。セックス、愛、朗読、戦後ドイツの不名誉についての、短くも豊かな物語。15歳の少年ミヒャエル・バーグは、謎めいた年上の女性ハンナとの激しい恋の虜になる。だが彼女の身の上についてはほとんど知らないうちに、ある日ハンナはミヒャエルの前から姿を消してしまう。…二度と彼女に会うことはないと思っていた彼だったが、戦慄(せんりつ)の再会が実現する。ナチスの過去を裁く法廷の被告席に、ハンナがいたのだ。彼女が筆舌に尽くせぬ重罪を犯していたことが明らかにされていく、その裁判の進行を追いつつ、ミヒャエルはとてつもなく大きな難問に取り組みはじめる。ホロコーストを知った自分たちの世代は、どう対処するべきか?「理解に苦しむものを理解できると思ってはいけないし、比較にならないものを比較してはいけない…。ぼくたちは、嫌悪と恥辱と罪の意識を抱えたまま、ただ黙っているべきなのだろうか?何のために?」
本書はボストン・ブックレビュー誌のフィスク・フィクション賞を獲得した。たぐいまれな明快な文章で、少ないページ数のなかで多くの悪の精神の問題に挑んでいる。世界がかつて知り得たなかで最悪といえる残虐行為に加担したのが親や祖父母、あるいは恋人であった場合、彼らを愛するという行為はどういったことなのか?文学を通しての贖罪(しょくざい)は可能か?シュリンクの文体は簡潔であり、比喩表現、会話といった文章の属性を問わず、余分なものはことごとくそぎ落とされている。その結果生まれたのが、ドイツの戦前と戦後の世代、有罪と無罪、言葉と沈黙の間に横たわる溝を浮き彫りにした、厳粛なまでに美しい本作なのである
|